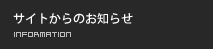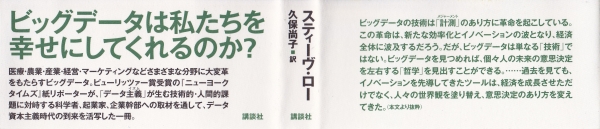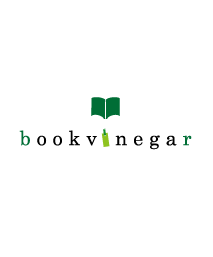
20代
経営
社会
テクノロジー
法律
営業術・交渉術
OL
金融機関関係者
コンサルタント
メーカーの従業員
経営企画部の人
全読者
人事部の人
営業マン
30代
学者
ものづくり
飲食店関係者
メンター
学生
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
データ・イズムの台頭
データ駆動型の発見を活用する動きは多くの分野で進行している。目先の目標として、まずは予測よりも観察だ。感知し、観察し、行動する、それがビッグデータの定石だ。ビッグデータ技術によって改善が進んでいる測定と監視は、観察に相当する。物事がはっきり見えるようになれば、賢明な行動をとれる見込みも高まるはずである。
定量的な世界で暮らす人々の数は増え続けている。データの価値はますます高まり、そこには英知すら宿り始めている。その英知こそが「データ・イズム」の真髄だ。どんな種類の意思決定も、経験と直観に頼るのではなく、データと解析に基づいて行われるべきである。当て推量や経験に基づいて結論を出すのは傍流になりつつある。
定量的な世界で暮らす人々の数は増え続けている。データの価値はますます高まり、そこには英知すら宿り始めている。その英知こそが「データ・イズム」の真髄だ。どんな種類の意思決定も、経験と直観に頼るのではなく、データと解析に基づいて行われるべきである。当て推量や経験に基づいて結論を出すのは傍流になりつつある。
点と点をつなぐ
データは文脈の中に置かれてこそ力を発揮する。データが蓄積されれば、より細部まで描き出せるようになり、描きだされたものは、知識となる。それがデータを理解するということだ。変化に富む大量データの供給源を新たに確保することも必要なことだ。しかし本当に大切なことは、重要な洞察や発見を生むような形で「点と点をつなぐこと」である。
データのつながりの1つが「相関」で、ある特定のデータパターンと現実世界の行動・活動に関連がみられる場合をいう。ビッグデータの流行の第1波は、相関を活用する形で押し寄せた。相関を見出すために「データの声を聞く」ことで、実際に有用かつ有益な結果が次々に生み出された。
このような相関は役に立つが、現実はもっと複雑で繊細だ。データの背後にある「全体像」がわかればデータの意味も見えてくるが、そのためには「失われた欠片」を埋めなければならない。それをするには「点と点をつなぐ」力が必要だ。
データのつながりの2つ目が「文脈」である。「意味上の関連」と言い換えることもでき、「相関」よりも少しだけ知識に近くなる。人間の言語は、その大部分が背景知識でできている。背景知識は時間をかけて蓄積されていくものである。全体像を明らかにし、文脈を読み取るために必要となる「失われた欠片」の正体は背景知識である。
データのつながりの1つが「相関」で、ある特定のデータパターンと現実世界の行動・活動に関連がみられる場合をいう。ビッグデータの流行の第1波は、相関を活用する形で押し寄せた。相関を見出すために「データの声を聞く」ことで、実際に有用かつ有益な結果が次々に生み出された。
このような相関は役に立つが、現実はもっと複雑で繊細だ。データの背後にある「全体像」がわかればデータの意味も見えてくるが、そのためには「失われた欠片」を埋めなければならない。それをするには「点と点をつなぐ」力が必要だ。
データのつながりの2つ目が「文脈」である。「意味上の関連」と言い換えることもでき、「相関」よりも少しだけ知識に近くなる。人間の言語は、その大部分が背景知識でできている。背景知識は時間をかけて蓄積されていくものである。全体像を明らかにし、文脈を読み取るために必要となる「失われた欠片」の正体は背景知識である。
人工知能の時代
IBMやグーグルなどで開発が進む人工知能が目指す認識モデルは、直観力と推測力を生み、さらに物事の「原因」を突き止めて理解する力をもたらす。それはもう「相関」の域を超えた「つながり」である。ビッグデータ時代の今後に期待されるのは、測定とモデルの関係が、少しずつ見直されながらも、本質的には損なわれずに維持されていくことである。
そして、今後は「どんな時にマシンを信頼するか」という問題が何度でも浮上することになる。必要になるのは、マシンがストーリーを語る力だ。自分について語り、自分がした処理の内容を簡単に説明することのできるマシンが必要となる。
そして、今後は「どんな時にマシンを信頼するか」という問題が何度でも浮上することになる。必要になるのは、マシンがストーリーを語る力だ。自分について語り、自分がした処理の内容を簡単に説明することのできるマシンが必要となる。