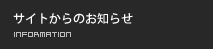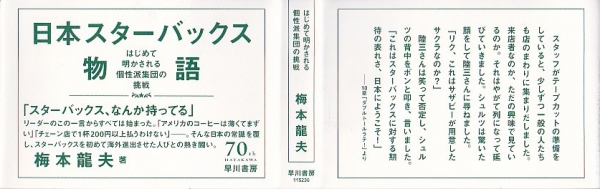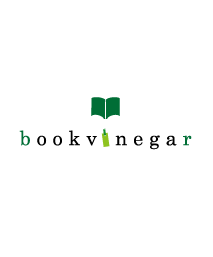
コンサルタント
ジャーナリスト
学生
30代
全読者
ノート術・読書術
プレゼンテーション
起業
商品企画部の人
リーダーシップ
ビジネスマナー
整理術・時間術
営業術・交渉術
中堅社員
メーカーの従業員
営業マン
思考法
法律
経営
文章術・図解術
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
きっかけ
1992年、サザビー創業者の実兄の角田雄二氏がロサンゼルスに進出したばかりのスターバックスのカリフォルニア1号店に「いいにおい」を嗅ぎ取り、一目惚れした。当時、スターバックスは、まだほとんど注目されていなかった。そして、スターバックス社長のハワード・シュルツに手紙を出した。すると、1週間後にシュルツ本人から直接電話がかかってきた。それは、日本での事業について話し合いたいのでシアトルに来て欲しいという「招待状」だった。シュルツは、角田雄二氏とサザビー社長の鈴木隆三氏の2人に会い、サザビーならスターバックスの価値を日本人に正しく伝え広めてくれるはずだと惚れ込んだ。
米国発のコーヒーは成功するのか
ここからしんどいプロセスが始まった。スターバックスは巨大なチェーンビジネスであり、いざ事業をやるとなれば、投下する資本も人的資源も半端ではない。サザビーは多店舗展開をしているとはいえ、1つ1つの事業がニッチマーケットを掘り起こすタイプで、個性と手作り感を大事にするビジネススタイル。一気に多店舗展開するノウハウも経験もなかった。そして、日本のコーヒーの方が断然おいしいというのが当時の日本人の常識だった。
ドトールに代表されるコーヒーチェーンは、多忙な人々が気楽に使える事を優先していた。良質なコーヒーを安価で提供するために、セルフサービスにした事が一番大きなポイントだった。飲み物と食べ物の組み合わせ、平均客単価、コーヒー豆などの物販比率は、米国スターバックスのデータとはずいぶん違っていた。スターバックスでは、大きなカップサイズのラテ系のドリンクにスイーツ系のパンやクッキーを一緒に買う客が、男女問わずいた。それに対し、ドトールを使うサラリーマンは、ドリップコーヒーだけ頼みタバコをふかす程度だった。
スターバックスの店舗は効率の悪さが目立つ。ただ、両ブランドではテイクアウトの比率が決定的に違った。テイクアウトが日本で成功するかどうかが、店舗の効率と利益に決定的に影響する事が予想された。
さらに大きな問題はコーヒーの単価だった。当時、ドトールはコーヒー1杯180円、プロントは160円。業界の専門家に聞くと、一様に「日本のコーヒーチェーンでは、1杯200円が限度」という意見だった。単価200円以下では、スターバックスはペイしない。
隆三氏は、スターバックスを日本でやるべきだとも、やるべきでないとも一切言わなかった。その代わりに、スターバックスは「かっこいい」とだけ表現した。隆三氏は、常に生産者ではなく、消費者の目線で商売を見ていた。「時代のこれから」を鋭く読み取るその目線の背景にあるのは「プロの否定」という姿勢だった。コーヒーのプロが一様にスターバックスを日本に持ってくるのに否定的であったのを聞いて、逆に行けると感じたのである。
ドトールに代表されるコーヒーチェーンは、多忙な人々が気楽に使える事を優先していた。良質なコーヒーを安価で提供するために、セルフサービスにした事が一番大きなポイントだった。飲み物と食べ物の組み合わせ、平均客単価、コーヒー豆などの物販比率は、米国スターバックスのデータとはずいぶん違っていた。スターバックスでは、大きなカップサイズのラテ系のドリンクにスイーツ系のパンやクッキーを一緒に買う客が、男女問わずいた。それに対し、ドトールを使うサラリーマンは、ドリップコーヒーだけ頼みタバコをふかす程度だった。
スターバックスの店舗は効率の悪さが目立つ。ただ、両ブランドではテイクアウトの比率が決定的に違った。テイクアウトが日本で成功するかどうかが、店舗の効率と利益に決定的に影響する事が予想された。
さらに大きな問題はコーヒーの単価だった。当時、ドトールはコーヒー1杯180円、プロントは160円。業界の専門家に聞くと、一様に「日本のコーヒーチェーンでは、1杯200円が限度」という意見だった。単価200円以下では、スターバックスはペイしない。
隆三氏は、スターバックスを日本でやるべきだとも、やるべきでないとも一切言わなかった。その代わりに、スターバックスは「かっこいい」とだけ表現した。隆三氏は、常に生産者ではなく、消費者の目線で商売を見ていた。「時代のこれから」を鋭く読み取るその目線の背景にあるのは「プロの否定」という姿勢だった。コーヒーのプロが一様にスターバックスを日本に持ってくるのに否定的であったのを聞いて、逆に行けると感じたのである。