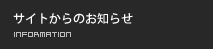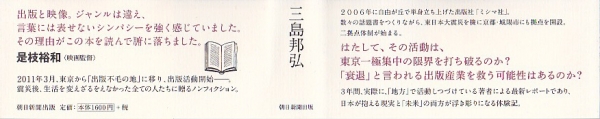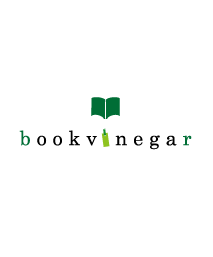
コミュニケーション
テクノロジー
ものづくり
中堅社員
メーカーの従業員
主婦
起業家
飲食店関係者
ビジネスマナー
人事部の人
イノベーション
商品企画部の人
リーダーシップ
経済
アジア
海外
マーケティング
整理術・時間術
メンター
マーケター
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
城陽プロジェクトの失敗
2013年1月、京都市内にオフィスを移そうという絵が迫ってきた。これは事実上の城陽プロジェクトの失敗を意味していた。1人のお客さんも来ない日々、来ない電車、著者の方との打合せをたった1人とも行えないで終わる1週間。調べものがあっても街中へ出るのに1時間。自由が丘メンバーとの情報共有の困難さ。切れる音声、切れるスカイプ映像。
結局、2013年3月末、結局、城陽から京都市内へオフィスを移す事になる。それは「日本のふつう」と謳った地での活動が実質的に終わりを告げる事を意味した。東京以外の地で出版社をというのは、出版不毛の地では所詮無茶な事だったのか。
結局、2013年3月末、結局、城陽から京都市内へオフィスを移す事になる。それは「日本のふつう」と謳った地での活動が実質的に終わりを告げる事を意味した。東京以外の地で出版社をというのは、出版不毛の地では所詮無茶な事だったのか。
脱記号
城陽に来る前、メディアの記号指向というものに内部にいながら辟易していた。記号指向とは、多様な要素を殺ぎ落とし、暴力的なまでに「ひとこと」にまとめてしまうやり方だ。「14歳」で「家出」をした「偏差値30」「金髪少女」の「起業」物語。言葉の中身はどうだっていい。記号だけで作られたコピーやキャプションを見て、消費者の方も条件反射する。
作り手たちも、そういう単純化した言葉で煽らないと「今の子達って反応ないっすよ」と、はなから諦めている。そうして「記号」のやりとりだけが行われる。「ミシマ社=自由が丘の古民家」「ミシマ社=アナログ」という硬直しきった記事が出回るようになった。しかし、それはほんの一面にしか過ぎない。そういう記号的存在にされてしまうのは耐え難かった。そのために脱記号を目指す。そう考えた結果が城陽への移動だった。
城陽にいる頃、よく時の流れが違うと感じた。同じ1分なのに、東京でバリバリ編集をしている時と比べて密度が明らかに違った。東京にいる同世代の仲間たちは「全国規模」の活躍を見せている。様々なジャンルで、新しい価値を生み出す仕事を次々にしている。明らかに焦っていた。
けれど、少なくとも表面上はそんな素振りは見せないよう努めた。どころか、各地でJOYOを連呼するようになった。JOYOを連呼する事で、「城陽」という記号の価値を高める事を目指していた。記号から逃れて地方へ進出したはずが、かえって記号に頼るようになった。
作り手たちも、そういう単純化した言葉で煽らないと「今の子達って反応ないっすよ」と、はなから諦めている。そうして「記号」のやりとりだけが行われる。「ミシマ社=自由が丘の古民家」「ミシマ社=アナログ」という硬直しきった記事が出回るようになった。しかし、それはほんの一面にしか過ぎない。そういう記号的存在にされてしまうのは耐え難かった。そのために脱記号を目指す。そう考えた結果が城陽への移動だった。
城陽にいる頃、よく時の流れが違うと感じた。同じ1分なのに、東京でバリバリ編集をしている時と比べて密度が明らかに違った。東京にいる同世代の仲間たちは「全国規模」の活躍を見せている。様々なジャンルで、新しい価値を生み出す仕事を次々にしている。明らかに焦っていた。
けれど、少なくとも表面上はそんな素振りは見せないよう努めた。どころか、各地でJOYOを連呼するようになった。JOYOを連呼する事で、「城陽」という記号の価値を高める事を目指していた。記号から逃れて地方へ進出したはずが、かえって記号に頼るようになった。
編集の仕事は1人ではできない
編集という仕事は1人でやるものではない。編集者は著者がいないと何の働きようもない存在だ。著者だけでなく、デザイナー、校正者、イラストレーター、ライター、そうした職種の方々と仕事をする事ではじめて「編集」は可能となる。城陽には、ここでしか進める事ができない仕事が皆無に近かった。
城陽にいる事で、本来すべき打合せが距離的な理由などで流れてしまうような事もあった。文字通り、仕事が成り立たなくなっていた。そういう事もあり、京都市内にオフィスを移す事を決断した。
城陽にいる事で、本来すべき打合せが距離的な理由などで流れてしまうような事もあった。文字通り、仕事が成り立たなくなっていた。そういう事もあり、京都市内にオフィスを移す事を決断した。