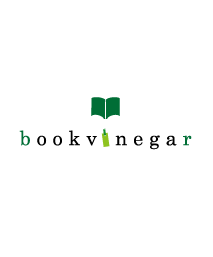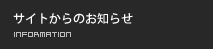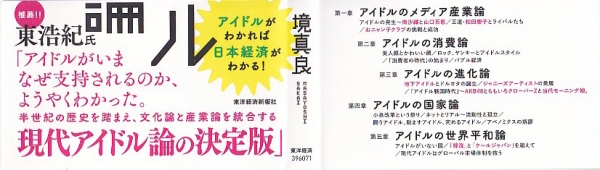ヘタレのためのアイドル
強いものに闘いを挑み、困難に挑戦し、源流に忠実たろうとする姿勢を「マッチョ」、反対にこれに背いて闘いから逃走する姿勢を「ヘタレ」と呼ぶ。この視点から見返すと、「アイドル現象」が示唆するのは、戦後日本は1980年代まで一貫してマッチョ主義を社会の公式規範として認めつつ、その実態は60年頃から次第にヘタレていったという事である。70年代以降、このヘタレ傾向は社会のメインストリームにすらなる。
60年代の日本は年功序列の給与体系と終身雇用を特徴とする「日本的経営」の勃興期から全盛期にかけての時期にあたる。いい大学、いい企業に入り、いい給料を得る。幸せな結婚をして、マイホームを建てて、老後は年金を得て幸せな人生を送る。それが若者に親世代が説いた「将来」だった。しかし、実際には競争に勝ち残ったものには大きな報酬があるという事実、自分がその競争に勝ち残れないという事実は、若者にとって自明だったかもしれない。
70年代に入り、将来に大きな夢を抱けなくなった多くの人達にとって、自らの主体性を実現できる可能性は「消費者」の次元にしか見出せなかった。人は、この消費活動による豊かさの実感を他者とのコミュニケーションの中で確認する必要があった。共通の嗜好で再編した「仲間」の重要度が増す中、アイドルのネタは仲間を形成するために最も有用なものの1つだった。
60年代の日本は年功序列の給与体系と終身雇用を特徴とする「日本的経営」の勃興期から全盛期にかけての時期にあたる。いい大学、いい企業に入り、いい給料を得る。幸せな結婚をして、マイホームを建てて、老後は年金を得て幸せな人生を送る。それが若者に親世代が説いた「将来」だった。しかし、実際には競争に勝ち残ったものには大きな報酬があるという事実、自分がその競争に勝ち残れないという事実は、若者にとって自明だったかもしれない。
70年代に入り、将来に大きな夢を抱けなくなった多くの人達にとって、自らの主体性を実現できる可能性は「消費者」の次元にしか見出せなかった。人は、この消費活動による豊かさの実感を他者とのコミュニケーションの中で確認する必要があった。共通の嗜好で再編した「仲間」の重要度が増す中、アイドルのネタは仲間を形成するために最も有用なものの1つだった。
アイドル現象の変遷
80年代以降、バブル経済の好景気が訪れ、日本社会と日本経済の閉塞感は、自己肯定的空気に一転する。「優勝劣敗原理」という正論を正面から捉える空気が日本に到来した事により、消費モードの中にはそれまで忌避してきた「ホンモノ」志向が強くなる。「アイドル」という「不完全なもの」の価値はどんどん落ちていき、「アーティスト」と呼ばれる実力派スターが再び評価される時代がやってきた。こうして「アイドル冬の時代」と言われる90年代につながっていく。
それから四半世紀、日本社会にはAKB48、ももいろクローバーZ、モーニング娘。など「アイドル」が再び溢れてしまう。デジタル化による効率化で「地域」「学校」など重要な中間組織が解体していく過程で、所属欲求を満たす機会は失われ、自分が孤独ではない事の確認行為は日々の生活の中の友人意識にシフトしていった。こうした状況の中で「アイドル」は自分が孤独でない事を確認するための装置の1つとしてもう一度召還された。
バブル以後進行したグローバル市場経済の浸透は、大きな夢を見る事なしに、それでも目の前に手の届く挑戦を諦めずに続けようとする、ヘタレているが懸命にマッチョに日々を生きる態度を持つ「ヘタレマッチョ」を生み出した。そして、現在アイドルはヘタレ達のマッチョ化を支える精神インフラとなった。
それから四半世紀、日本社会にはAKB48、ももいろクローバーZ、モーニング娘。など「アイドル」が再び溢れてしまう。デジタル化による効率化で「地域」「学校」など重要な中間組織が解体していく過程で、所属欲求を満たす機会は失われ、自分が孤独ではない事の確認行為は日々の生活の中の友人意識にシフトしていった。こうした状況の中で「アイドル」は自分が孤独でない事を確認するための装置の1つとしてもう一度召還された。
バブル以後進行したグローバル市場経済の浸透は、大きな夢を見る事なしに、それでも目の前に手の届く挑戦を諦めずに続けようとする、ヘタレているが懸命にマッチョに日々を生きる態度を持つ「ヘタレマッチョ」を生み出した。そして、現在アイドルはヘタレ達のマッチョ化を支える精神インフラとなった。