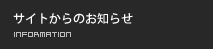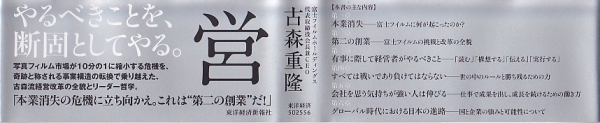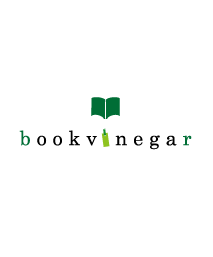
経営企画部の人
ものづくり
ノート術・読書術
20代
テクノロジー
金融機関関係者
起業
30代
接客業の人
OL
飲食店関係者
マーケティング
社会
Web
科学
政治家
教育
営業術・交渉術
中堅社員
リーダーシップ
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
デジタル化の兆し
銀を使った写真感光材料のビジネスが脅かされる可能性は、80年代の初頭から予想されていた。というのも、富士フイルムの主な事業分野である、写真、印刷、医療の三大画像分野で、この頃からデジタル化の兆しが現れ始めたからだ。写真の分野では、銀の代わりに光電素子で光をキャッチして画像を作る電子カメラ、今でいうデジタルカメラの開発がこの頃から始まり、エレクトロニクスメーカーや写真関連メーカーでこうしたモデルが試作された。デジタル化の波に富士フイルムとしてどう対応すべきか議論がなされ、3つの戦略に集約された。
①デジタル技術の自社開発を進める
CCDを自社で開発するなど、早くからデジタルカメラへの取り組みを進め、1990年代の末から数年間は、世界のデジタルカメラ市場で30%のシェアを持った。
②感光材料事業の寿命を伸ばす
デジタルが追いつけない水準にアナログの銀塩写真フィルムの技術を進歩させ、感光材事業の延命を図った。
③新規事業を開発する
1990年代の中頃からは、従来のイメージング事業の周辺分野である、インクジェットの事業や光ディスクの研究に取り組んだ。また、医薬品の開発にも着手した。
だが、これらの新規事業の多くは、その後頓挫する事になる。その最大の理由は、写真フィルムという、高収益でシェアも高い絶対的なコアビジネスが、まだ伸びていたからだ。
①デジタル技術の自社開発を進める
CCDを自社で開発するなど、早くからデジタルカメラへの取り組みを進め、1990年代の末から数年間は、世界のデジタルカメラ市場で30%のシェアを持った。
②感光材料事業の寿命を伸ばす
デジタルが追いつけない水準にアナログの銀塩写真フィルムの技術を進歩させ、感光材事業の延命を図った。
③新規事業を開発する
1990年代の中頃からは、従来のイメージング事業の周辺分野である、インクジェットの事業や光ディスクの研究に取り組んだ。また、医薬品の開発にも着手した。
だが、これらの新規事業の多くは、その後頓挫する事になる。その最大の理由は、写真フィルムという、高収益でシェアも高い絶対的なコアビジネスが、まだ伸びていたからだ。
本業消失
2000年頃から、写真はほとんどデジタルに切り替わっていき始めた。この年、一般用のフィルムやカラー印画紙を扱う写真事業は、富士フイルムの売上の6割を占め、利益の2/3を稼ぎ出していた。そして、この年が、写真フィルム事業のピークだった。翌年からカラーフィルムの需要は、世界規模で急激に落ち始める。年に20、30%という勢いで、市場が消失し、写真フィルム事業はわずか5年で赤字に転落した。
一方、デジタルカメラ事業は、世界でトップシェアを握った。しかし、その先に待ち構えていたのは、毎年15%も価格が下がり続けるという熾烈な価格競争で、写真フィルムの収益の激減をカバーする事は困難だった。
一方、デジタルカメラ事業は、世界でトップシェアを握った。しかし、その先に待ち構えていたのは、毎年15%も価格が下がり続けるという熾烈な価格競争で、写真フィルムの収益の激減をカバーする事は困難だった。
第二の創業
2003年に取り組み始めたのが、企業改革の計画の策定だった。そこでは「徹底的な構造改革」「新たな成長戦略の構築」「連結経営の強化」という3つの基本方針を打ち出した。
そして、2006年から、写真フィルム事業の、世界中に保有していた大規模な生産設備や販売組織、現像所などの再編に着手し、リストラを断行した。一方で、大きな可能性を秘めていると判断した事業には大胆に投資をした。例えば、その1つが、液晶パネルの生産に欠かせない「偏光板保護フィルム」事業への投資である。これは、スマートフォンなどでも需要が拡大し、その事業は重要な収益の柱に成長している。
そして、2006年から、写真フィルム事業の、世界中に保有していた大規模な生産設備や販売組織、現像所などの再編に着手し、リストラを断行した。一方で、大きな可能性を秘めていると判断した事業には大胆に投資をした。例えば、その1つが、液晶パネルの生産に欠かせない「偏光板保護フィルム」事業への投資である。これは、スマートフォンなどでも需要が拡大し、その事業は重要な収益の柱に成長している。
- トップページ
- ビジネス書要約・書評
- 魂の経営
- 要約