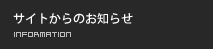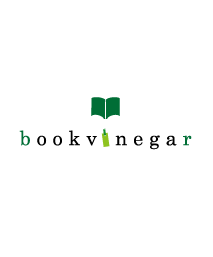
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
超簡単! 仕事を効率化する集中力の高め方
勉強、仕事、読書などを効率化するためには、集中力が欠かせない。その集中力を高めるには、18分で時間を区切るだけ。誰にでもできるシンプルなタスク管理術を紹介しています。
 超短要約
超短要約
■なぜ18分なのか?
これまで集中力を考える本では「90分」という時間を1つのまとまりとして考えられる事が多かった。大学の授業が1コマ90分というのが多いのも、こうした従来の考え方が基本になっている。しかし、90分という時間は、集中力を持続するには長く困難な時間設定ではないか。
中学や高校の授業は50分くらいが普通である。しかし、講義形式では、先生の指示に従って頭を使うため、主体的な集中力をもって自分をコントロールするのとは少し違う。主体的にハイレベルの集中力を持続するには、50、60分でも長すぎる。また、30分でもその日のバイオリズムが必ずしも高くない状態の人にとっては長いと感じる。
心理学の分野では、何か作業をする際の集中力に関して「初頭努力」「終末効果」「中だるみ」という用語を用いて分析する。つまり、どんなタスクでも、最初と最後に高い集中が見られ、真ん中に中だるみの時間がある。
「18分」という時間は、誰にでもどんなタスク内容でも「初頭努力」をもたらす可能性を持ち、かつ十分な「終末効果」を期待できる時間設定である。「18分」というのは、「15分プラス3分」であり、この3分が味噌となる。「15分」というのは、ラジオの英語番組などにも用いられており、集中できかつ一定のタスクの達成も見込まれる最小単位だと考えられている。しかし、「終末効果」にとっての満足な時間を得るには15分では少し短い。これが18分だと驚くべき効果を上げるという事が次第にわかってきた。
まず「18分」という時間設定が中途半端なので、休みを挟んでもう少し頑張ろうという気持ちが起こりやすいし、15分が経って少し疲れを感じても「後3分」という頑張りが起こり、「終末効果」が高まる。
 著者 菅野 仁
著者 菅野 仁
1960年生まれ。宮城教育大学教育学部教授 東北大学文学部助手、青森公立大学経営経済学部助教授、宮城教育大学教育学部助教授などを経て、2006年より同大学教育学部教授。 専攻は社会学(社会学思想史・コミュニケーション論・地域社会論)
この本を推薦しているメディア・人物
![エコノミスト 2013年 3/5号 [雑誌] エコノミスト 2013年 3/5号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61PRcE9-MyL._SL60_.jpg) エコノミスト 2013年 3/5号 [雑誌]
エコノミスト 2013年 3/5号 [雑誌]詩人 和合 亮一 |
![週刊 ダイヤモンド 2013年 3/16号 [雑誌] 週刊 ダイヤモンド 2013年 3/16号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51F7Y51aADL._SL60_.jpg) 週刊 ダイヤモンド 2013年 3/16号 [雑誌]
週刊 ダイヤモンド 2013年 3/16号 [雑誌]三省堂書店営業本部課長 鈴木 昌之 |
章の構成 / 読書指針
| 章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| はじめに | p.7 | 4分 |  |
| 序章 今日も一日無駄にした! | p.17 | 5分 |  |
| 第1章 「根性なし」でもできることって | p.27 | 11分 |  |
| 第2章 「やる気」が起きないとき | p.49 | 12分 |    |
| 第3章 これが「18分」集中法だ! | p.75 | 22分 |      |
| 第4章 面倒なインプットに効く | p.121 | 13分 |    |
| 第5章 アウトプットにはこう使え! | p.149 | 6分 |   |
| 第6章 心と体の声を聞く | p.161 | 6分 |  |
| 「18分」集中法の実践の効果 | p.173 | 7分 |  |
| おわりに | p.188 | 1分 |  |
この本に影響を与えている書籍(参考文献、引用等から)
 心と体がスッキリする「1日15分」瞑想法 (PHP文庫)
心と体がスッキリする「1日15分」瞑想法 (PHP文庫)[Amazonへ] |
 読書と社会科学 (岩波新書)
読書と社会科学 (岩波新書)[Amazonへ] |
 社会認識の歩み (岩波新書)
社会認識の歩み (岩波新書)[Amazonへ] |