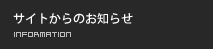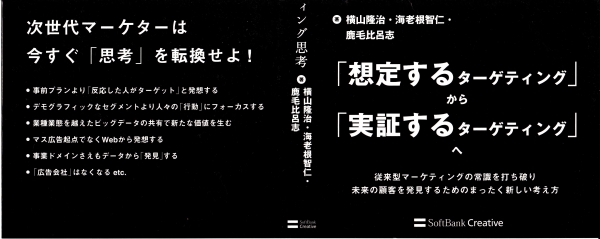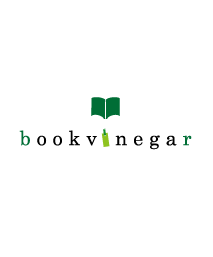
教育
リーダーシップ
経営者
法律
ビジネスモデル
経営
メーカーの従業員
経済
ジャーナリスト
プレゼンテーション
社会
科学
ビジネスマナー
20代
営業術・交渉術
投資家
マーケティング
ソーシャル
ものづくり
起業
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
反応した人がターゲット
DSPが登場し、ディスプレイ広告を1表示ずつ買い付ける仕組みになった事で、3つの構造変化が起きた。
①広告を掲載面を選んで買うのではなく、「誰に配信するか」で買う
②買い手側の都合で広告を買い付ける
③広告代理店の営業マンの「手売り」から、オンライン購入する
広告を「枠」から「人」へ送る事が可能になった事で、広告に反応した人を把握する事ができるようになった。
新たなターゲット論を一言で表現すると、「反応した人がターゲット」という事になる。これまで、ターゲットは事前に想定するものであったが、これからはマーケティング施策を遂行する中で実証していくものになる。
①広告を掲載面を選んで買うのではなく、「誰に配信するか」で買う
②買い手側の都合で広告を買い付ける
③広告代理店の営業マンの「手売り」から、オンライン購入する
広告を「枠」から「人」へ送る事が可能になった事で、広告に反応した人を把握する事ができるようになった。
新たなターゲット論を一言で表現すると、「反応した人がターゲット」という事になる。これまで、ターゲットは事前に想定するものであったが、これからはマーケティング施策を遂行する中で実証していくものになる。
現在の顧客から未来の顧客を見つけ出す
ビッグデータ時代のマーケティングの一つの方向に、既存顧客から将来の顧客をターゲティングするという考え方がある。新規顧客獲得には、広く遍なく広告を打つ事が常套手段であった。どこにいるかわからない新規顧客に、認知から促すためには、そうするしかなかった。
しかし、実は認知からスタートする新規顧客獲得にさえも、すでに顧客化したユーザーのデータを利用する事ができる。そもそも顧客化する人とはどんな人達なのか、どんな文脈に関心があり、どんなメッセージに反応するのか。そういった事を、既存顧客を分析すると、新規顧客への広告ターゲティングやメッセージ開発に生かせる。
今後は、コンバージョン(顧客化)する人にあってコンバージョンしない人にはない文脈を発見する事が重要になってくる。ネットで抽出できるデータから意味を読み取って、リアルな世界を含むマーケティング全体に応用するのが望ましい。
しかし、実は認知からスタートする新規顧客獲得にさえも、すでに顧客化したユーザーのデータを利用する事ができる。そもそも顧客化する人とはどんな人達なのか、どんな文脈に関心があり、どんなメッセージに反応するのか。そういった事を、既存顧客を分析すると、新規顧客への広告ターゲティングやメッセージ開発に生かせる。
今後は、コンバージョン(顧客化)する人にあってコンバージョンしない人にはない文脈を発見する事が重要になってくる。ネットで抽出できるデータから意味を読み取って、リアルな世界を含むマーケティング全体に応用するのが望ましい。
反応者志向のマーケティングへ
従来はマーケティングセグメントと言えば、ユーザーを①人口属性、②地理、③心理、④行動という基準を軸に、横割りで区分してきた。しかし、ビッグデータ時代に重要なのは、主に行動基準であり、①〜③の基準にユーザーを分類する事にはさほど意味がない。
反応者志向のマーケティングにおいて、企業はまず、対象をゆるやかに想定する。重要なのは、実証されたユーザーの反応である。そして、反応したユーザーを母集団から抽出して、そこでPDCAをきめ細かく回していく。最初にパターン化ありきではなく、反応したユーザーでプロファイリングし、ターゲット全体像を拡大解釈していくべきなのだ。また、反応者と同じような行動をとっているユーザーを新たな想定顧客として考慮していく。
これこそがビッグデータ時代の新たなマーケティング思考であり、新しいターゲティングの手法なのである。
反応者志向のマーケティングにおいて、企業はまず、対象をゆるやかに想定する。重要なのは、実証されたユーザーの反応である。そして、反応したユーザーを母集団から抽出して、そこでPDCAをきめ細かく回していく。最初にパターン化ありきではなく、反応したユーザーでプロファイリングし、ターゲット全体像を拡大解釈していくべきなのだ。また、反応者と同じような行動をとっているユーザーを新たな想定顧客として考慮していく。
これこそがビッグデータ時代の新たなマーケティング思考であり、新しいターゲティングの手法なのである。