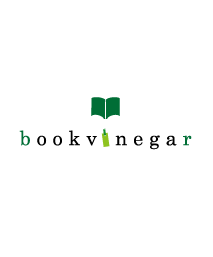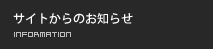経済二重人格
神経経済学の研究で得られた重要な発見の一つは、人が決断している間、脳の異なる部位同士が競い合っているということである。つまり、感情を担当する部分と理屈をつかさどる部分の対立が起きている。この現象は、人が異時点間の問題に直面した時、なぜ矛盾した結論を出すのかを説明してくれるかもしれない。
・短期の衝動的な自己と長期の辛抱強い自己
今日の10ドルと明日の11ドルでは、今日の10ドルを選ぶが、一年後に10ドルもらうか、一年と一日後に11ドルもらうかという選択肢だと、長い方を選ぶ。
・内発的動機づけと外発的動機づけ
保育所が子供の迎えに遅れてくる保護者に罰金を科すと、逆に遅刻が増える。遅刻の罰金によって、遅れる行為に値段がつき、保護者にとって遅刻が公認される行為になってしまう。
・相対報酬
他の従業員の業績に比べて、その人の業績がどうかで給料が決まる相対的報酬制度では、逆に生産性を下げる。この制度では、度を超えて頑張り過ぎると、同僚の仕事を侵害し、同僚の給料を減らしてしまう事から、大半の人はゆるいペースで働く事を選ぶ。
何が人を動機付けるのか解明するには、経済学は人間行動の衝動について、抽象的な前提を設定するのをやめて、事例研究にもっと重点をおき、経済の意思決定者を詳しく観察しなければならない。
・短期の衝動的な自己と長期の辛抱強い自己
今日の10ドルと明日の11ドルでは、今日の10ドルを選ぶが、一年後に10ドルもらうか、一年と一日後に11ドルもらうかという選択肢だと、長い方を選ぶ。
・内発的動機づけと外発的動機づけ
保育所が子供の迎えに遅れてくる保護者に罰金を科すと、逆に遅刻が増える。遅刻の罰金によって、遅れる行為に値段がつき、保護者にとって遅刻が公認される行為になってしまう。
・相対報酬
他の従業員の業績に比べて、その人の業績がどうかで給料が決まる相対的報酬制度では、逆に生産性を下げる。この制度では、度を超えて頑張り過ぎると、同僚の仕事を侵害し、同僚の給料を減らしてしまう事から、大半の人はゆるいペースで働く事を選ぶ。
何が人を動機付けるのか解明するには、経済学は人間行動の衝動について、抽象的な前提を設定するのをやめて、事例研究にもっと重点をおき、経済の意思決定者を詳しく観察しなければならない。
幸福の追求
昔ながらの経済学者は、誰もが効用を最大にしようと励み、自由に使えるお金と自由に消費する機会に恵まれるほど効用が増すという前提から出発する。この前提が本当なら、親の倍の所得や富を手にした世代は、自分の生活にはるかに満足しているはずだ。
ところがそうはいかない。貧しい国だけに限れば、生活全般の満足度は平均所得の増加にともなって高くなる。しかし、最低生存水準に達した途端、この相関関係は崩れてしまう。経済学者イースタリンは、所得がこれ以上増えても人々の幸せにほとんど寄与しなくなる上限を購買力平価で15000〜20000ドルとした。
幸福研究の成果によれば、絶対所得は、他の要素に比べると影が薄い。ほとんどの人は、他人と比べた時の自分の立場を何より気にかける。所得と消費は地位を決める。多くの人にとって、高い所得に付随する高い社会的地位の方が、そのお金で買えるものによって増える効用より重要である。
また、人はどんな事にも慣れてしまう。生活水準の向上も例外ではなく、所得が増えれば、その人が実感する欲求や要求もそれに伴って大きくなる。
ところがそうはいかない。貧しい国だけに限れば、生活全般の満足度は平均所得の増加にともなって高くなる。しかし、最低生存水準に達した途端、この相関関係は崩れてしまう。経済学者イースタリンは、所得がこれ以上増えても人々の幸せにほとんど寄与しなくなる上限を購買力平価で15000〜20000ドルとした。
幸福研究の成果によれば、絶対所得は、他の要素に比べると影が薄い。ほとんどの人は、他人と比べた時の自分の立場を何より気にかける。所得と消費は地位を決める。多くの人にとって、高い所得に付随する高い社会的地位の方が、そのお金で買えるものによって増える効用より重要である。
また、人はどんな事にも慣れてしまう。生活水準の向上も例外ではなく、所得が増えれば、その人が実感する欲求や要求もそれに伴って大きくなる。