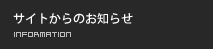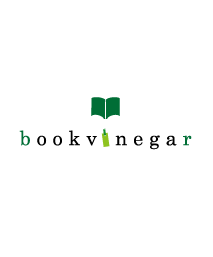
リーダーシップ
主婦
営業術・交渉術
経営
コンサルタント
金融機関関係者
経営者
健康
派遣社員
生き方
働き方
戦略
中堅社員
プレゼンテーション
接客業の人
思考法
学者
文章術・図解術
コミュニケーション
政治
-
2020-05-15
-
2019-08-20
-
2019-06-25
-
2013-04-17
-
2013-01-17
既存事業の業績悪化
経営者は、過去に成功体験があるとそれにこだわり、経営の路線を誤ることがある。その後の環境の変化を見誤るからである。先代の小倉康臣氏も戦後の市場が変化した時、成功体験が足かせとなり、長距離輸送への参入が遅れ、経営危機に陥った。
終戦から10年、これまで長距離輸送は、鉄道の仕事と見なされていたが、道路の改良とトラックの質の向上により、荷積みが速いトラックが利用されるようになった。しかし、ヤマト運輸は、康臣氏のトラックの守備範囲は100km以内との信念により、関東一円のローカル路線に閉じこもったままであった。
結果として長距離路線への参入に5年遅れることで、既に主な荷主は同業者に抑えられ、貨物が集まらないという苦労をすることになった。
トラック業界は、伸びる会社と伸びない会社に分かれた。シェアの大きい会社は効率によって、ますます伸びるのに対し、競争会社は同じことをやっている限り、追いつくのは難しい。
ヤマト運輸の事業は、近隣輸送のトラック運送、国鉄の仕事である通運、百貨店配送が主な事業であった。しかし、長距離輸送への出遅れ、国鉄の斜陽化、オイルショックによる百貨店の業績悪化を原因として、いずれの事業も業績が悪化し始めた。
終戦から10年、これまで長距離輸送は、鉄道の仕事と見なされていたが、道路の改良とトラックの質の向上により、荷積みが速いトラックが利用されるようになった。しかし、ヤマト運輸は、康臣氏のトラックの守備範囲は100km以内との信念により、関東一円のローカル路線に閉じこもったままであった。
結果として長距離路線への参入に5年遅れることで、既に主な荷主は同業者に抑えられ、貨物が集まらないという苦労をすることになった。
トラック業界は、伸びる会社と伸びない会社に分かれた。シェアの大きい会社は効率によって、ますます伸びるのに対し、競争会社は同じことをやっている限り、追いつくのは難しい。
ヤマト運輸の事業は、近隣輸送のトラック運送、国鉄の仕事である通運、百貨店配送が主な事業であった。しかし、長距離輸送への出遅れ、国鉄の斜陽化、オイルショックによる百貨店の業績悪化を原因として、いずれの事業も業績が悪化し始めた。
個人宅配へ
そこで、目をつけたのが個人の荷物宅配であった。個人宅配の市場は、郵便局しか競合がいない。しかし、採算が取れないだろうとのことで、民間は誰も参入していなかった。
個人宅配は「いつどの家から、どのような荷物を運ぶのか決まっていないので集配効率が悪い」という課題があった。個人の荷物をいかに集荷するか。そこで取次店の設置を思いついた。
個人宅配市場を開拓するのに必要なものは、取次店だけでなく、全国規模の配達ネットワークも不可欠である。そこで、地域ごとに営業拠点を置く、ハブ・アンド・スポーク・システムという方法をとった。
配送ネットワークが構築できたとして、問題は採算が取れるかであった。しかし、ネットワークの上を荷物がどんどん流れれば、必ず損益分岐点を超えると考えていた。損益分岐点を超えるかについては、集積車1台あたりで、一日何個を扱えば良いかを考えた。一台で集配個数をいかに増やすか。新しい市場に転換しても儲かるはずだと確信した。
極端に効率の悪い個人宅配事業は絶対に赤字が出るという先入観によって、役員全員から反対されたが、労働組合の現場の危機意識によって始まることになった。
荷物の総量をいかに増やすか。このために徹底した「商品化」を行った。わかりやすい料金体系、ネーミングなど。また、差別化として、「翌日配達」が実行された。
サービスとコストは常にトレードオフの関係にある。宅配事業で決めたことは「サービスが先、利益は後」ということであった。
個人宅配は「いつどの家から、どのような荷物を運ぶのか決まっていないので集配効率が悪い」という課題があった。個人の荷物をいかに集荷するか。そこで取次店の設置を思いついた。
個人宅配市場を開拓するのに必要なものは、取次店だけでなく、全国規模の配達ネットワークも不可欠である。そこで、地域ごとに営業拠点を置く、ハブ・アンド・スポーク・システムという方法をとった。
配送ネットワークが構築できたとして、問題は採算が取れるかであった。しかし、ネットワークの上を荷物がどんどん流れれば、必ず損益分岐点を超えると考えていた。損益分岐点を超えるかについては、集積車1台あたりで、一日何個を扱えば良いかを考えた。一台で集配個数をいかに増やすか。新しい市場に転換しても儲かるはずだと確信した。
極端に効率の悪い個人宅配事業は絶対に赤字が出るという先入観によって、役員全員から反対されたが、労働組合の現場の危機意識によって始まることになった。
荷物の総量をいかに増やすか。このために徹底した「商品化」を行った。わかりやすい料金体系、ネーミングなど。また、差別化として、「翌日配達」が実行された。
サービスとコストは常にトレードオフの関係にある。宅配事業で決めたことは「サービスが先、利益は後」ということであった。