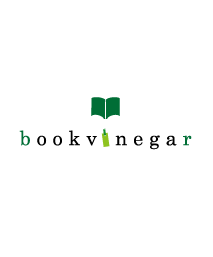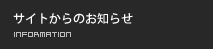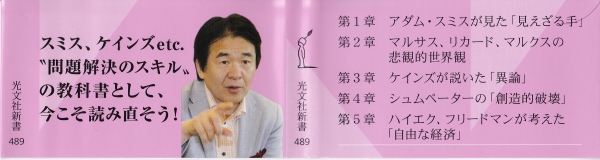経済古典の今日的な意義とは?
アダム・スミス、マルサス、リカード、マルクス、ケインズ、シュムペーター、ハイエク、フリードマン、ブキャナンの経済理論を取り上げ、狭義の学問としてではなく、経済の本質を見る目と、困難な問題を解決する基本力を高めることに焦点をあて、「経済古典」の今日的意義を考える。
小泉内閣で構造改革を手がけた著者が、現代の経済や政策のあり方に結びつけて分かり易く「経済古典」を解説する。
 超短要約
超短要約
多くの経済古典は目の前の問題解決のために書かれた。経済古典の今日的意義とは、狭義の学問としてではなく、経済の本質を見る目と、困難な問題を解決する基本力を高めてくれるところにある。
経済運営の基本はスミスの指摘の様に、やはり「市場の見えざる手」を活用することである。これなくして、経済運営はあり得ない。同時に、ときにケインズのいうような大胆な政府介入が必要になる場合がある。そして、その背後にイノベーションが必要であり、シュンペーターが主張した企業も一国経済も「成功の故に失敗する」という教訓を忘れてはならない。
また、ハイエク、フリードマン、ブキャナンの警告にある様に、あくまで自由を基本に、政府が肥大化するリスクを避けるために絶えざる工夫が必要だ。
残念ながら日本の経済政策は、これらをすべて無視、または軽視している。経済思想のなかに逃げ込むのではなく、具体的なスキルを学び、活用しなくてはならない。
 著者 竹中平蔵
著者 竹中平蔵
1951年生まれ。慶應義塾大学教授、グローバルセキュリティ研究所所長 1973年、大学卒業後、日本開発銀行入行。その後、大蔵省財政金融研究所、大阪大学経済学部助教授、ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授などを歴任。 1998年に「経済戦略会議」メンバーとなる。2001年に経済財政政策担当大臣に就任し、金融担当大臣、経済財政政策・郵政民営化担当大臣、総務大臣などを務め、小泉純一郎内閣の「構造改革」を主導した。2006年より現職
この本を推薦しているメディア・人物
|
|
![週刊 東洋経済 2011年 1/8号 [雑誌] 週刊 東洋経済 2011年 1/8号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GbbPLTe2L._SL60_.jpg) 週刊 東洋経済 2011年 1/8号 [雑誌]
週刊 東洋経済 2011年 1/8号 [雑誌] |
章の構成 / 読書指針
| 章名 | 開始 | 目安 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| はじめに | p.3 | 10分 |    |
| 第1章 アダム・スミスが見た「見えざる手」 | p.21 | 24分 |     |
| 第2章 マルサス、リカード、マルクスの悲観的世界観 | p.63 | 15分 |     |
| 第3章 ケインズが説いた「異論」 | p.89 | 22分 |     |
| 第4章 シュムペーターの「創造的破壊」 | p.129 | 24分 |     |
| 第5章 ハイエク、フリードマンが考えた「自由な経済」 | p.171 | 27分 |     |
| おわりに | p.220 | 1分 |    |
この本に影響を与えている書籍(参考文献、引用等から)
 経済学および課税の原理〈上巻〉 (岩波文庫)
経済学および課税の原理〈上巻〉 (岩波文庫)[Amazonへ] |
 資本論〈第1巻(上)〉 (マルクス・コレクション)
資本論〈第1巻(上)〉 (マルクス・コレクション)[Amazonへ] |
 雇用、利子および貨幣の一般理論〈上〉 (岩波文庫)
雇用、利子および貨幣の一般理論〈上〉 (岩波文庫)[Amazonへ] |
 経済発展の理論―企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究〈上〉 (岩波文庫)
経済発展の理論―企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究〈上〉 (岩波文庫)[Amazonへ] |
 資本主義と自由 (日経BPクラシックス)
資本主義と自由 (日経BPクラシックス)[Amazonへ] |
 経済学をつくった巨人たち―先駆者の理論・時代・思想 (日経ビジネス人文庫)
経済学をつくった巨人たち―先駆者の理論・時代・思想 (日経ビジネス人文庫)[Amazonへ] |
 いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ―有効需要とイノベーションの経済学
いまこそ、ケインズとシュンペーターに学べ―有効需要とイノベーションの経済学[Amazonへ] |
 国富論 国の豊かさの本質と原因についての研究(上)
国富論 国の豊かさの本質と原因についての研究(上)[Amazonへ] |
ユーザーのしおりメモ (0)
- トップページ
- ビジネス書要約・書評
- 経済古典は役に立つ (光文社新書)
- 書評サマリー